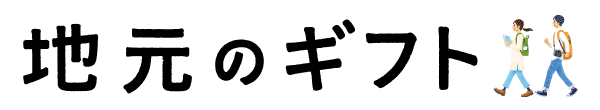お中元の時期を知り尽くそう!贈るタイミングや地域ごとの違いを解説
2024/12/06
BeeNiiお中元お祝い
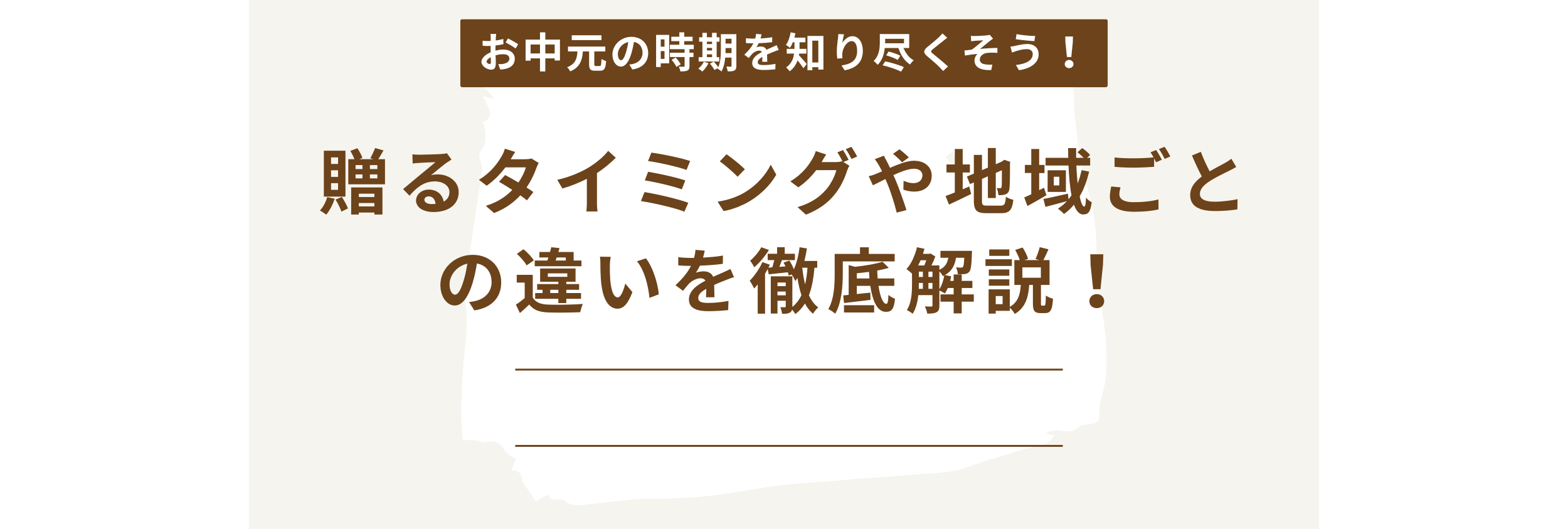
お中元の時期とは?
お中元を贈る時期は、地域によって異なります。
関東と関西
・関東: 7月初旬から7月15日頃まで
・関西: 旧暦に合わせて1ヶ月遅れの8月1日から15日まで
その他
・北海道・東海・関西・中国・四国: 7月中旬~8月15日
・沖縄: 7月下旬~8月上旬
近年では、お中元は全国的に7月の中旬までに贈るのが一般的になっており、この時期に贈ると失礼に当たらないでしょう。
ただし、お中元も早割りなどでお得に購入できるケースが多くなっており、最近では全国的にも6月下旬等に準備・贈る人も増え、年々早まる傾向にあります。 百貨店などのお中元商戦も6月初旬に始まるケースが増加しています。
関東と関西
・関東: 7月初旬から7月15日頃まで
・関西: 旧暦に合わせて1ヶ月遅れの8月1日から15日まで
その他
・北海道・東海・関西・中国・四国: 7月中旬~8月15日
・沖縄: 7月下旬~8月上旬
近年では、お中元は全国的に7月の中旬までに贈るのが一般的になっており、この時期に贈ると失礼に当たらないでしょう。
ただし、お中元も早割りなどでお得に購入できるケースが多くなっており、最近では全国的にも6月下旬等に準備・贈る人も増え、年々早まる傾向にあります。 百貨店などのお中元商戦も6月初旬に始まるケースが増加しています。
お中元の起源と意義
お中元の起源は、中国の旧暦7月15日に行われる「中元節(ちゅうげんせつ)」と呼ばれる行事です。中元節は、先祖の霊を供養し、罪を赦してもらうための行事でした。
これが日本に伝来し、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)と結びついて、先祖供養と世話になった人への感謝の気持ちを伝える行事へと変化したといわれています。
その後江戸時代になると、商人が得意先への支払いとともに7月15日に贈り物をする習慣が生まれます。その習慣は明治時代に太陽暦の変更とともに8月となり、これが日本のお中元の起源となりました。
現在、お中元は先祖供養やお世話になった人への感謝、暑中見舞いの機会として定着しています。
これが日本に伝来し、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)と結びついて、先祖供養と世話になった人への感謝の気持ちを伝える行事へと変化したといわれています。
その後江戸時代になると、商人が得意先への支払いとともに7月15日に贈り物をする習慣が生まれます。その習慣は明治時代に太陽暦の変更とともに8月となり、これが日本のお中元の起源となりました。
現在、お中元は先祖供養やお世話になった人への感謝、暑中見舞いの機会として定着しています。
お中元の正しい時期
お中元の正しい時期は、地域によって異なりますが、一般的には7月上旬から7月15日頃までとされています。ただし近年は、6月下旬から7月15日頃までにお中元を贈る人も増えています。これは、早割などの割引制度を利用してお得に購入できるためです。
しかし、お中元はあくまでも「相手を気遣う気持ちを表すための贈り物」であるため、上記の日程にこだわりすぎる必要はありません。相手の都合や地域性を考慮した上で、最適な時期に贈るのがマナーです。
地域別の中元時期
・関東・東北: 7月初旬から7月15日頃まで
・東海・関西・中国・四国: 7月中旬から8月15日頃まで
・北海道: 7月中旬から8月15日頃まで
・九州: 8月1日から8月15日頃まで
・沖縄: 旧暦の7月15日まで
しかし、お中元はあくまでも「相手を気遣う気持ちを表すための贈り物」であるため、上記の日程にこだわりすぎる必要はありません。相手の都合や地域性を考慮した上で、最適な時期に贈るのがマナーです。
地域別の中元時期
・関東・東北: 7月初旬から7月15日頃まで
・東海・関西・中国・四国: 7月中旬から8月15日頃まで
・北海道: 7月中旬から8月15日頃まで
・九州: 8月1日から8月15日頃まで
・沖縄: 旧暦の7月15日まで
地域によるお中元の差
お中元は、本来は仏教行事である「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来するものであり、先祖の霊を供養するとともに、日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝える贈り物です。しかし、現在ではお中元は仏教的な意味合いよりも、夏の風物詩として定着しており、贈る時期や内容は地域によって少しずつ異なっています。
1.定番のギフト
・関東・東北: ビール、そうめん、洗剤など
・東海・関西・中国・四国: 果物、お菓子、ギフトカタログなど
・北海道: 海鮮、スイーツ、ギフトセットなど
・九州: 焼酎、和菓子、グルメギフトなど
・沖縄: 泡盛、お菓子、沖縄そばなど
2.その他
・関東では、7月7日の七夕にちなんで「七夕お中元」と呼ばれる贈り物をすることもあります。
・沖縄では、旧暦の7月15日を「中元」と呼び、お中元を贈ります。
1.定番のギフト
・関東・東北: ビール、そうめん、洗剤など
・東海・関西・中国・四国: 果物、お菓子、ギフトカタログなど
・北海道: 海鮮、スイーツ、ギフトセットなど
・九州: 焼酎、和菓子、グルメギフトなど
・沖縄: 泡盛、お菓子、沖縄そばなど
2.その他
・関東では、7月7日の七夕にちなんで「七夕お中元」と呼ばれる贈り物をすることもあります。
・沖縄では、旧暦の7月15日を「中元」と呼び、お中元を贈ります。
関東地方のお中元時期
関西地方のお中元の時期は、7月中旬から8月15日頃までです。ただし、近年ではお中元の時期が早まっており、7月15日頃までに相手に届くように贈るのが一般的になっています。関東地方と比べると、関西地方のお中元の時期は1ヶ月ほど遅くなります。これは、関西地方では旧暦の「お盆」が8月に行われるためです。
関西地方のお中元時期
関西地方のお中元の時期は、7月中旬から8月15日頃までです。ただし、近年ではお中元の時期が早まっており、7月15日頃までに相手に届くように贈るのが一般的になっています。
関東地方と比べると、関西地方のお中元の時期は1ヶ月ほど遅くなります。これは、関西地方では旧暦の「お盆」が8月に行われるためです。
関東地方と比べると、関西地方のお中元の時期は1ヶ月ほど遅くなります。これは、関西地方では旧暦の「お盆」が8月に行われるためです。
お中元のマナーと注意点
お中元は、お世話になった方へ感謝の気持ちを伝える大切な夏の風物詩です。しかし、せっかくの気持ちが台無しにならないよう、いくつか注意すべき点があります。
1. 時期
早めの時期がおすすめです。近年は、早割などの割引制度を利用してお得に購入できるため、6月下旬から7月15日頃までにお中元を贈る人も増えています。また、お盆休みなどの都合で、相手が不在の場合は避けた方がよいでしょう。
2. ギフト
相手が喜ぶものを推測して選びましょう。高額な贈り物をするのは避け、相手の負担にならない程度のものを選びましょう。仏教関係の品物、お酒(相手が下戸の場合)、賞味期限が短いものは避けましょう。
3.熨斗(のし)
表書きには「中元」と書き、自分の名前を下に記入します。ただし、地域によっては「暑中御見舞」や「残暑御見舞」とする場合もあります。
4.その他
相手が喪中の場合は、お中元を贈るのは避けましょう。また、相手が遠方にいる場合は、配送手配を忘れずに行いましょう。
お中元は、日ごろお世話になっている方への感謝の気持ちを伝える大切な機会です。上記を参考に、失礼のないようにお中元を贈りましょう。
参考ページ
1. 時期
早めの時期がおすすめです。近年は、早割などの割引制度を利用してお得に購入できるため、6月下旬から7月15日頃までにお中元を贈る人も増えています。また、お盆休みなどの都合で、相手が不在の場合は避けた方がよいでしょう。
2. ギフト
相手が喜ぶものを推測して選びましょう。高額な贈り物をするのは避け、相手の負担にならない程度のものを選びましょう。仏教関係の品物、お酒(相手が下戸の場合)、賞味期限が短いものは避けましょう。
3.熨斗(のし)
表書きには「中元」と書き、自分の名前を下に記入します。ただし、地域によっては「暑中御見舞」や「残暑御見舞」とする場合もあります。
4.その他
相手が喪中の場合は、お中元を贈るのは避けましょう。また、相手が遠方にいる場合は、配送手配を忘れずに行いましょう。
お中元は、日ごろお世話になっている方への感謝の気持ちを伝える大切な機会です。上記を参考に、失礼のないようにお中元を贈りましょう。
参考ページ
お中元の贈り方の基本
1.配送業者
ヤマト運輸、佐川急便、郵便局など、主要な配送業者が対応しています。また、クール便が必要な場合は、事前に確認しておきましょう。
2.送料
ギフトの大きさや重量、配送先によって異なります。送料無料のショップもありますので、事前に確認しておきましょう。
3.メッセージカード
ギフトにメッセージカードを添えたい場合は、事前に用意しておきましょう。メッセージカードには、感謝の気持ちを簡潔に書きましょう。
ヤマト運輸、佐川急便、郵便局など、主要な配送業者が対応しています。また、クール便が必要な場合は、事前に確認しておきましょう。
2.送料
ギフトの大きさや重量、配送先によって異なります。送料無料のショップもありますので、事前に確認しておきましょう。
3.メッセージカード
ギフトにメッセージカードを添えたい場合は、事前に用意しておきましょう。メッセージカードには、感謝の気持ちを簡潔に書きましょう。
お中元の品物選びのポイント
お中元は、日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝える夏の風物詩です。せっかくの気持ちが台無しにならないよう、品物選びのポイントをまとめました!
1. 相手の好みやニーズに合わせる
これが最も重要です。相手の好きなもの、嫌いなもの、アレルギーなどを事前にリサーチしておき、相手が喜ぶ顔を想像しながら、品物を選びましょう。高額な贈り物をするのは避け、相手の負担にならない程度のものを選ぶことも大切です。
2. 定番の品目を押さえる
ビール、そうめん、洗剤、ギフトカタログ、果物、お菓子などが定番です。これらの品目は、比較的どなたにも喜ばれる傾向があります。季節感のある品物を選ぶのも良いでしょう。
3. 避けた方がよいもの
仏教関係の品物
お酒(相手が下戸の場合)
賞味期限が短いもの
刃物、履物、下着、肌着など(縁起が悪いとされるもの)
金銭や商品券(金品授受と捉えられかねない)
4. 熨斗(のし)をつける
表書きには「中元」と書き、自分の名前を下に記入します。地域によっては「暑中御見舞」や「残暑御見舞」とする場合もあります。
水引は紅白蝶結びを使い、内のしにするのが基本です。
1. 相手の好みやニーズに合わせる
これが最も重要です。相手の好きなもの、嫌いなもの、アレルギーなどを事前にリサーチしておき、相手が喜ぶ顔を想像しながら、品物を選びましょう。高額な贈り物をするのは避け、相手の負担にならない程度のものを選ぶことも大切です。
2. 定番の品目を押さえる
ビール、そうめん、洗剤、ギフトカタログ、果物、お菓子などが定番です。これらの品目は、比較的どなたにも喜ばれる傾向があります。季節感のある品物を選ぶのも良いでしょう。
3. 避けた方がよいもの
仏教関係の品物
お酒(相手が下戸の場合)
賞味期限が短いもの
刃物、履物、下着、肌着など(縁起が悪いとされるもの)
金銭や商品券(金品授受と捉えられかねない)
4. 熨斗(のし)をつける
表書きには「中元」と書き、自分の名前を下に記入します。地域によっては「暑中御見舞」や「残暑御見舞」とする場合もあります。
水引は紅白蝶結びを使い、内のしにするのが基本です。
まとめ:お中元の時期とマナーを理解しよう
今回は、お中元を贈る時期やマナーについて解説しました。マナーに気を付けて、日頃の感謝を伝えましょう!