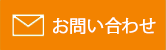夏と冬の贈り物、お中元とお歳暮の違いやおすすめギフト紹介
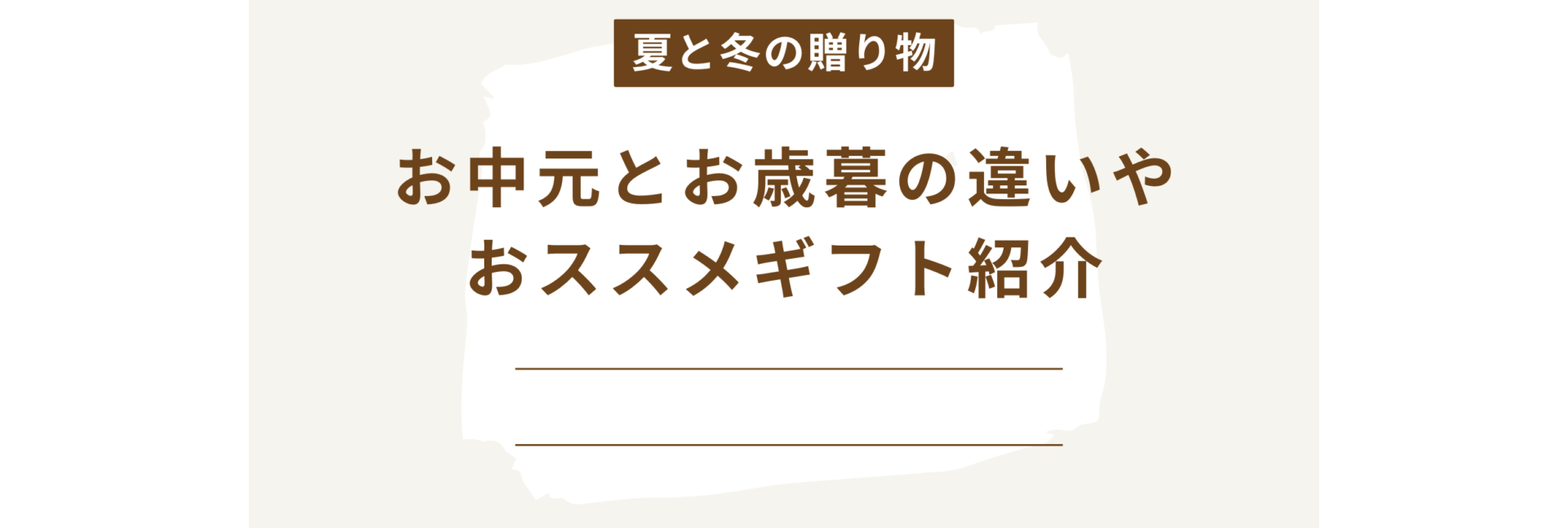
お中元とお歳暮の意味とは
お中元とお歳暮は、「お世話になりました」という感謝の気持ちと心遣いを込めて、日頃お世話になっている方や目上の方に贈るギフトです。
現在では、お中元とお歳暮は感謝の気持ちを伝えるだけでなく、暑気払いや親睦を深める目的も込められています。
お中元の起源と目的
お中元の起源は、中国の旧暦7月15日に行われる「中元節(ちゅうげんせつ)」と呼ばれる行事です。
中元節は、先祖の霊を供養し、罪を赦してもらうための行事でした。
これが日本に伝来し、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)と結びついて、先祖供養と世話になった人への感謝の気持ちを伝える行事へと変化したといわれています。
その後江戸時代になると、商人が得意先への支払いとともに7月15日に贈り物をする習慣が生まれます。その習慣は明治時代に太陽暦の変更とともに8月となり、これが日本のお中元の起源となりました。
現在、お中元は先祖供養やお世話になった人への感謝、暑中見舞いの機会として定着しています。
お歳暮の起源と目的
お歳暮の起源は、古代中国の「三元」という考え方に由来します。三元とは、1年のうち3つの重要な節目のことを指します。上元(1月15日)、中元(7月15日)、下元(10月15日)と呼ばれ、それぞれ神仏への供養や先祖供養が行われていました。
日本には、この三元の一つである中元が仏教行事として伝来し、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれるようになりました。盂蘭盆会は、先祖の霊を供養する行事でしたが、次第に親戚や目上の方へ贈り物をする習慣へと変化していきました。
室町時代頃になると、「御霊祭(みたままつり)」と呼ばれる、家々の先祖の霊を祭る行事が盛んになりました。御霊祭では、神仏や先祖への供え物として、餅や果物、酒などが捧げられていました。これが、お歳暮の起源と言われています。
江戸時代になると、商人たちが年末に得意先へ挨拶回りをする際に、手土産を持参することが一般的になりました。これが、現代のお歳暮の原型となったと考えられています。
このように、お歳暮は古代中国の三元、日本の盂蘭盆会、御霊祭、そして江戸時代の商人たちの挨拶回りの習慣が融合して生まれた風習と言えます。
お歳暮は、1年間お世話になった方への感謝の気持ちを伝えるとともに、新年への希望を込めた贈り物でもあります。近年では、形式にとらわれず、自由なスタイルで贈られることも増えています。
お中元・お歳暮の選び方のポイント
お中元とお歳暮は、日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝える風物詩です。せっかくの気持ちが台無しにならないよう、品物選びのポイントをまとめました!
1. 相手の好みやニーズに合わせる
これが最も重要です。相手の好きなもの、嫌いなもの、アレルギーなどを事前にリサーチしておき、相手が喜ぶ顔を想像しながら、品物を選びましょう。高額な贈り物をするのは避け、相手の負担にならない程度のものを選ぶことも大切です。
2. 定番の品目を押さえる
ビール、そうめん、洗剤、ギフトカタログ、果物、お菓子などが定番です。これらの品目は、比較的どなたにも喜ばれる傾向があります。季節感のある品物を選ぶのも良いでしょう。
3. 避けた方がよいもの
・仏教関係の品物
・お酒(相手が下戸の場合)
・賞味期限が短いもの
・刃物、履物、下着、肌着など(縁起が悪いとされるもの)
・金銭や商品券(金品授受と捉えられかねない)
4. 熨斗(のし)をつける
表書きには「中元」と書き、自分の名前を下に記入します。地域によっては「暑中御見舞」や「残暑御見舞」とする場合もあります。
水引は紅白蝶結びを使い、内のしにするのが基本です。
相手の好みを考慮した選び方
お中元やお歳暮を贈る際は、何よりも相手の好みと一致しているかどうかが最も重要です。相手が好きなものや、普段買わないようなちょっと贅沢なものを贈ると、より喜んでもらえる可能性が高くなります。
また、相手のことを気にかけて、選んでくれたことが伝わり、より感謝の気持ちが伝わりやすくなるでしょう。
反対に相手の好みや事情を無視して贈り物を選ぶと、場合によっては失礼になってしまうこともあります。
相手の好みを考慮するポイント
相手が好きな食べ物や飲み物、趣味などを普段の会話から聞き出すと、贈り物を選ぶ際の参考になります。
家族構成によっては、喜ばれるものが変わってきます。例えば、小さなお子さんがいる家庭であれば、子供向けの菓子やおもちゃなどが喜ばれる可能性もあります。また、相手に食物アレルギーや苦手なものがある場合は、避けて選ぶようにしましょう。
どうしても相手の好みが分からない場合は、定番の品物を選ぶのも一つの方法です。例えば、洗剤やタオル、お菓子などの消耗品は、どなたでも喜ばれる定番の品物です。
価格帯による選び方
価格帯の目安
一般的には3,000円~5,000円程度が相場とされていますが、目上の人やお世話になっている人には、5,000円~10,000円程度のものを選ぶことも多いです。親しい友人や知人であれば、3,000円以下のものでも良いでしょう。
価格を決める際のポイント
目上の人やお世話になっている人には、ある程度の価格帯のものを選ぶのがマナーですが、親しい友人や知人であれば、そこまで高価なものでなくても構いません。
また、相手が裕福な場合は、高価なものであっても問題ありませんが、そうでない場合は、相手に負担にならないような価格帯のものを選びましょう。無理をして高価なものを選ぶ必要はありません。自分の予算内で、相手に喜んでもらえるものを調べて選びましょう。
人気のお中元・お歳暮ギフトランキング
楽天市場によると、お中元・お歳暮で人気の商品は以下のようなものです。
1.うなぎ
お中元シーズンは土用の丑の日にも近いことから、うなぎは定番人気です。蒲焼きには迫力あるうな丼が作れる立派なサイズのものや、食べやすいようカットされたもの、ひつまぶしに適した刻みタイプなどがあります。香ばしい香りに加え、見た目もこんがりきつね色で食欲をそそります。上品な味わいの白焼きも根強い人気で、蒲焼きとの「紅白」セット商品も多数販売中です。名店や名産地の味を贈りましょう。
2.アイスクリーム
夏にはアイスを食べたくなるという方も多いはず。そこで、子どもの多い家庭や甘党の方には、アイスクリームギフトもおすすめです。自社牧場で丹精込めて育てた牛の乳をそのまま使った商品や、厳選したフレッシュミルクで作られた商品など、こだわりのアイスクリームが豊富にラインナップしています。フルーツなどのトッピングをたくさん乗せ、彩り豊かに仕上げた写真映えするアイスも人気です。
3.ゼリー
アイスと並んで、お中元で人気のスイーツの1つがゼリーです。みかん・ぶどう・桃・さくらんぼなど味の種類が豊富で、彩りも美しいので見た目にも楽しめます。冷やして食べれば、つるんとのどごしが良くフルーツの味も存分に感じられて、夏の暑さを爽やかに吹き飛ばしてくれるでしょう。農園や果樹園で愛情をこめて生産された新鮮な果物を使用した商品もあり、普段食べるゼリーとはひと味違ったおいしさを感じられます。
その他にも、洋菓子や海鮮、そうめんや果物なども人気の品物です。
参考ページ
毎年人気のお中元・お歳暮ギフト
毎年人気のお中元ギフトには、夏に嬉しいアイスクリームやゼリー、ビールのほか、土用の丑の日に食べられるうなぎや、見た目も華やかな洋菓子やフルーツなどがおすすめです。
また、お歳暮ギフトでは日持ちするハム・ソーセージや、出汁・ふりかけ、冬に嬉しい高級茶などが人気となっています。家族で楽しめる詰め合わせや、日本酒なども定番です。
まとめ
今回は、お中元とお歳暮の歴史や選び方のポイント、おすすめの品物などをご紹介しました。
お中元とお歳暮は、感謝を伝える大切な行事です。しっかりと下調べをして、気持ちを伝えましょう!